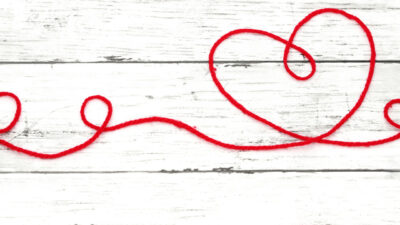最近、現れだしたリナの奇行。
危ないと思わせる行動が増えた。
止めようとすると、ふとした拍子に逆切れ――最近のリナは、いつも何かに苛ついているようだった。
理由がわからない上に限度を越えると、こちらも限界が訪れる。
しかも、今回は踏み込んだらヤバイ領域だった。
最初はただ単に、いつものようにリナを諌めようとしただけだった。
なのに、リナの挑発といえるような言動は止まらない。
気づいたら、こっちもどこで止めていいのか分からなくなっていた。
それでなくても、最近は自分の感情をもてあまし、どうしていいのか分からないところへ――だ。こんな風に挑発されたら、それに乗ってコトを進めてしまえという誘惑の声が強まる。
リナの服の中に手をもぐりこませ、温かみのある肌をまさぐった。
「……ぃやああっ!」
リナの甲高い声が上がった。
それが、その気になった男を止める術になるとでも思っているのだろうか?
それに、ここまででないにしろ、関係の進展を望んだのはリナだって同じ――そう思って、いや、そう言い訳をして、リナを壁際に押し付けたまま、もぐりこませた手はそのままで、もう片方の手でリナのあごを掴んで固定して、首筋に舌を這わせる。
長年続いた曖昧な関係は、もう普通に告白して付き合って――という域から外れてしまっている気がして、このままなし崩しにしてしまえという囁きが、何処からか聞こえた気がした。
魔の誘惑と言えるようなそれにくらりとする。
本当に、それほどまでにこの曖昧な関係は居心地が良かった。
だから、壊したくなかった。
でも、どこかで壊したかった。
リナを拘束しながら、言い訳めいたことを考えていると、耳元で――性格には耳よりも少し上で――リナのすすり泣く声が聞こえた。
気丈なリナのこと、泣き喚く――などと大げさなことはしない。
でも、声を押し殺してもたまに漏れてしまう呻き声を聞いてしまったら、思い切り冷や水をかけられた気がして、体の熱が冷めていった。
驚いた、というのが一番だった。
自分が招いた結果だと、どこかで理解しているのか、オレを罵倒するようなことは言わない。
けど、怖いのか、あのリナが声を押し殺して涙を流していた。
よく見れば必死に耐えていたのか、唇をかみ締めていたようで血がうっすらと滲んでいた。
こんなリナを見ては、もう手の出しようがないわけで――
服の中にもぐりこんでいた手を出して、代わりに目を瞑って固まっているリナの頬をぺちりと叩いた。
「分かったか。男ってリナが思っているより危険なんだよ」
どこまでも卑怯なオレは、自分のしたことを棚上げして、男というものせいに摩り替えた。
リナの涙にぬれた目がオレを睨みつけるが、それ以上なにか言ってくることはなかった。
これで、罵倒でもなんでもあれば、少しは会話になって何処へかは分からないけど、道は繋がるかもしれない。でも睨みつけられるだけでは、これ以上、進みようがないんだ。
「これに懲りたらおとなしく、鍵かけて寝るんだぞ。いいな、リナ」
一方的に言い放ち、隣の扉を開いて出た。
しばらくして、カチャ、と小さな音が聞こえる。先ほどのようなことがないように、言うことを聞いて鍵をしっかりかけたらしい。
確認してからオレは自分の部屋へ戻った。
部屋に戻ってベッドにどさりと座り込んで、深いため息をついた。
互いに気づいている限界。
でも、どうしていいのか分からない。
子ども扱いしていれば、保護者と被保護者だ。でも、周りは不自然な目で見る。そりゃそうだろう。オレは金髪に青い目だ。リナは栗色の髪に赤みを帯びた茶色の目。顔立ちも似たところがない。どう見ても、兄妹という言葉で片付けられないだろう。
そんなオレたちが二人だけで旅をしていると、好奇心の目で見るやつらが多い。
いや、まだリナと会った頃――あの頃なら、それほど違和感はなかった。リナが女らしくなったことによって、少しずつ、周囲の目が変わったのだ。
あの二人はいったいどういう関係なのか――と。
周囲の目など気にしなければいい。最初はそう思った。
でも、駄目なんだ。オレ自身が変わりだしていたから。
周りの声が聞こえるたびに、嫌でも意識していく自分の気持ち。
気持ちを告げられない不甲斐ない自分に苛つき、周囲の目を気にしないリナの行動に苛ついた。
「なにやってんだ、オレは……」
ぼやきながらもう一度深いため息をついた。
情けない。いい年して……こんな余裕のない状態は初めてだ。家を出た頃も余裕がないと思ったけど、今は別の意味で余裕がない。散々リナを子ども扱いしたけど、これじゃあ、人のことを言えないじゃないか。
ごろりとベッドに転がって仰向けになると、暗い天井が見える。さらに視線を移していけば、気づくと窓があって、そこから星が小さく瞬いていた。
窓はともかく、暗さのために天井と壁があいまいで、どこまで天井で、何処から壁になるのか分からない。
まるで、今のオレたちの関係に似てる。
くっきりと、線を引いたらどうなるんだろうか?
線を引いたらすっきりするんだろうか?
いや、しない。線を引いて立った場所による。
異性として好きというのなら、このまま一緒に居ても問題ない。
でも仲間のほうだったら、まもなく別れが訪れるだろう。いつまでも何も変わらず旅をしていけるわけがない。
かといって、線引きしなくても、別れの時はカウントダウン待ちだ。普通なら、年頃になれば誰かと恋をして、そして家庭を持つ。
あの破天荒なリナだって、「まだ恋もしてないのに」とか「白馬の王子さま♪」などと言っていたから、多少の憧れはあるだろう。
……ってか、ゼフィーリアに着いたとき、うまく自己紹介できなかったのが敗因だよな。
リナの“父ちゃん”に驚いている間に、ろくな挨拶もできないまま、リナの“姉ちゃん”こと、ルナさんといつの間にかに剣でやりあっていた。リナの姉だけあって、すごく強いというか(あとで、赤の竜神の騎士とかいうのだと聞いて驚いた)、一瞬たりと気を抜けない状態だった。
そんな打ち合いが終わった後は、もう汗だくで思考が吹っ飛んでいた。
気づくと、オレにそれを言わせないためか、ルナさんの稽古はあそこにいる間続いたし、夜になるとおっさんに酒攻めにされた。
そして、気づくと進展なしに終わってたんだ。
あーもう、過去に戻れるなら、あのときに戻って過去のオレをド突きたい。
ぐるぐる考えてたうちに眠ったのか、次に気づいたときは部屋の中が明るくなっていた。
急いで下に下りると、リナはすでに朝飯を食っていた。ちらりとこちらを一瞥すると、何事もなかったかのようにまた食べ始める。
慎重にリナに「おはよう」といって向かいに座ると、「おはよう。ご飯いらないと思ったわ。来ないから」と素っ気ないが、何もなかったかのような返事が返ってきた。
お……お願いだから、ここで何事もなかったようにしないでくれ……
心の中でガクリとしながら、それでも朝飯を頼んで来るのを待った。
昨夜のことがショックだったのか、それとも信じてないのか、オレの錯乱だと思ったのかもしれないか――どちらにしろ、リナは問題はなかったかのように振舞う。
だから余計に進めない。
ふ、と気づく。何事もなかったかのように振舞うリナ。
目の前でいつものように食事をとるリナを見て、ふと疑問に思った。
リナはいったいどうしたいんだろう?